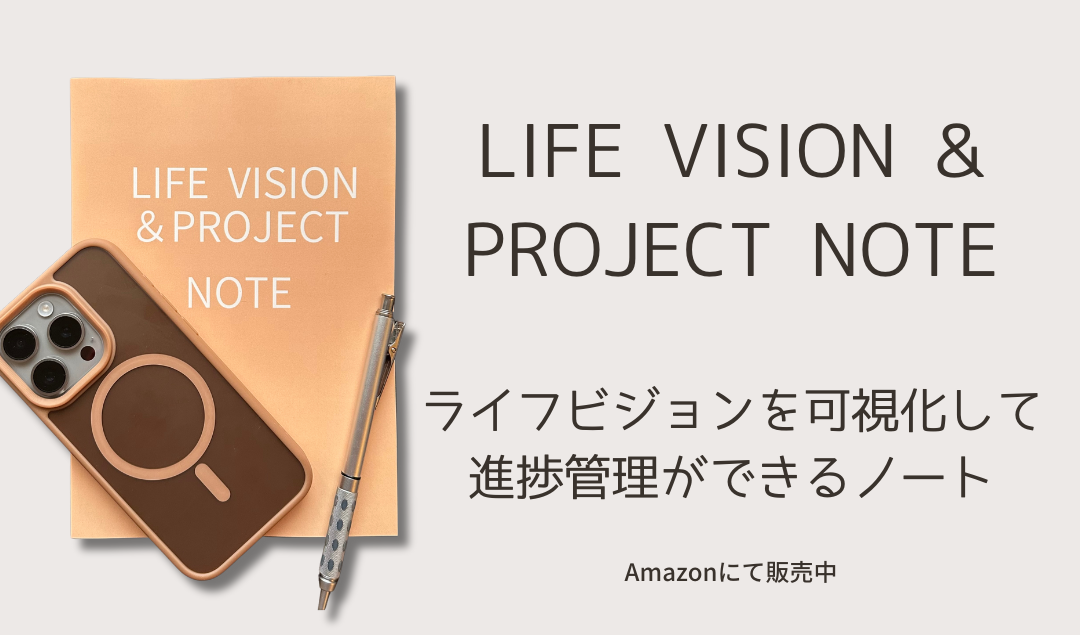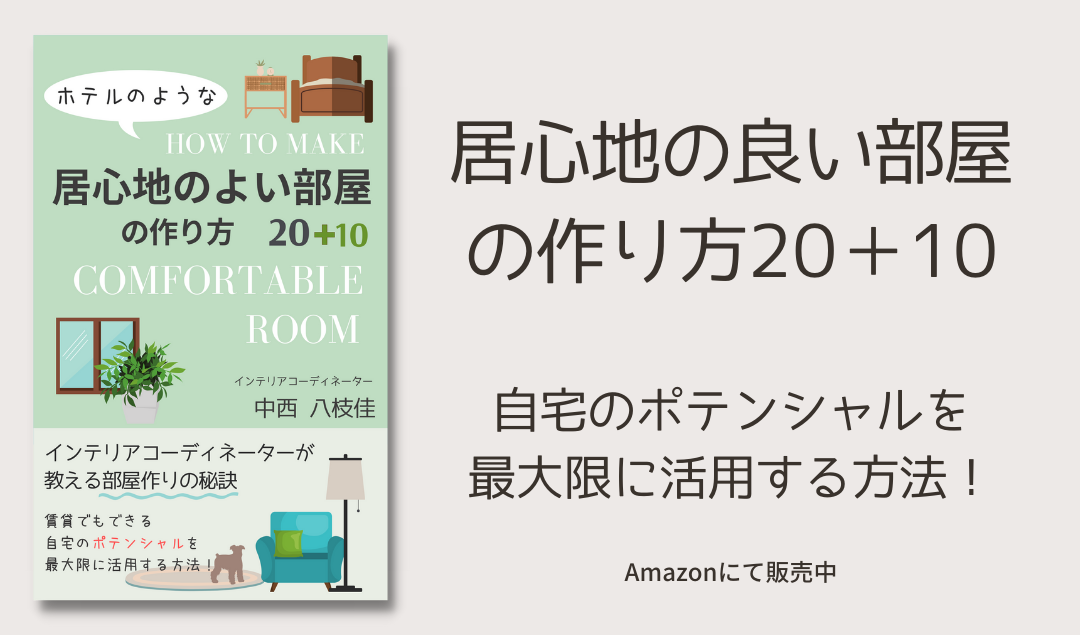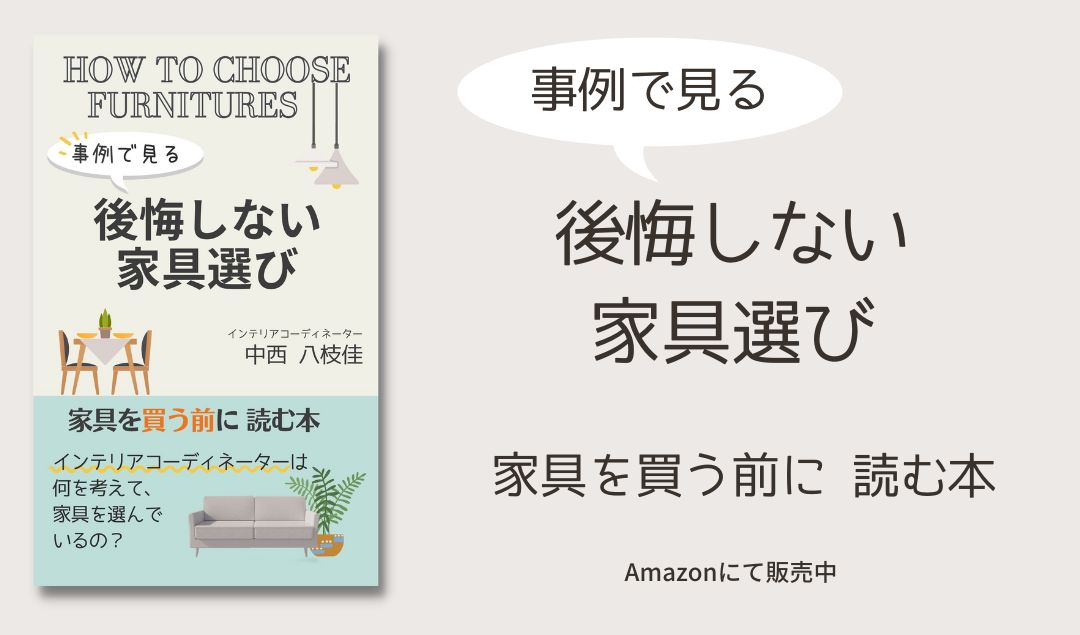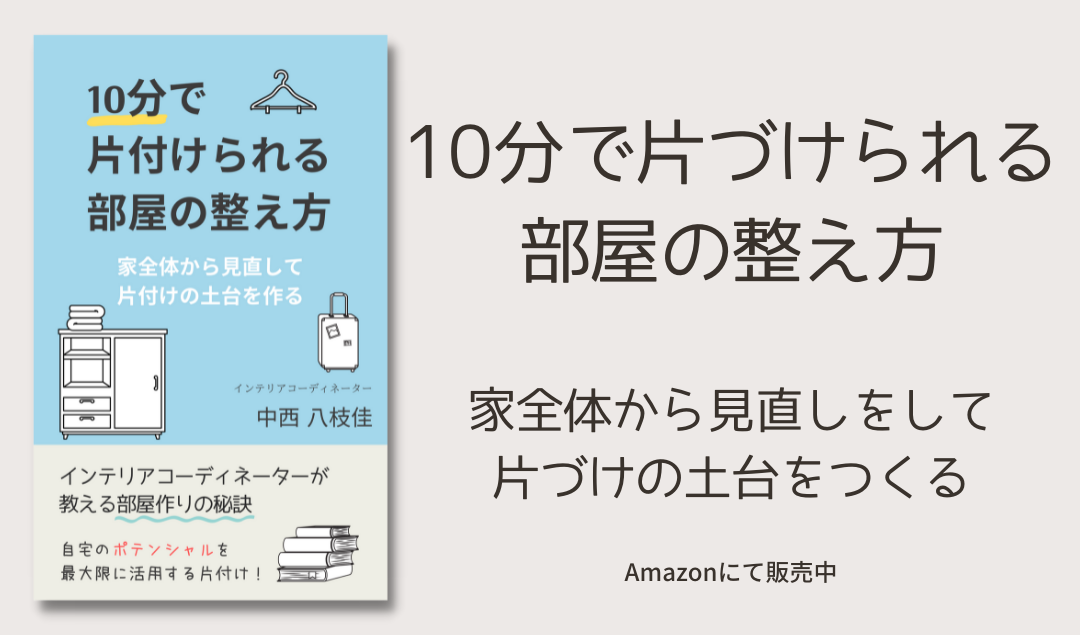大正、昭和と今の家事の時間から、自分の時間の使い方を振り返る 平日1日の家事の時間は何時間?

1961年(昭和36年)のころは、家事の時間は1日に平均10時間2分使っていたそうです。今の家事の時間と比べると、8時間以上も違うのにびっくりしました。その8時間は、自分はどう使っているのか?振り返りつつ、今時間を有意義にすごすために心掛けていることを紹介します。
私の家事の時間は1日どれぐらいかかっている?
私の朝の時間を振り返ると、
朝(2018年の私)
お弁当の用意 10分
朝ごはんの用意 10分
食事の片付け 食洗機に入れる 8分
洗濯機に入れる、乾燥機を使うものとの仕分け 、乾いたものの仕分け 10分
洗濯物たたむ 5分
ルンバが動きやすいように、床片付け 2分 以上でだいたい45分
夕方(2018年の私)
食事の用意 20分〜30分
片付け 10分 以上でだいたい40分
1日平均すると、1時間25分でした。これは、その日のやる気、気力、他に邪魔するものがないかによっても前後しますが、平均こんな感じでしょうか。
と2018年は書いていました。現在2025年の私も振り返ることにしました。
朝(2025年の私 息子高校生と大学生)
お弁当の用意 10分
朝ごはんの用意 10分
食事の片付け 食洗機に入れる 8分
洗濯機に入れる⇒夫
洗濯ものを干す 5分
洗濯物たたむ ⇒たたむことをやめてかごに入れるようにしました
ルンバが動きやすいように、床片付け 5分
子どもが大きくなったこともあり、なるべく手を抜くことにしています。また、子どもの成長に伴い、ここに書いていない子どものサポートの時間が減ったので、7年前よりは手がかからないので時間に余裕があるような気がします。
夕方(2025年の私 息子高校生と大学生)
食事の用意 片付け で30分~1時間
それ以外にもお風呂の準備 数分
以前よりは、慌てて夕食の用意をする必要がなくなり、のんびりごはんをつくるようになりました。
その他名もなき家事も含めて、1日2時間ぐらいは何かしています。
大正、昭和の時代の家事と、家事にかかった時間はどれぐらい?

先日(2018年)訪れた江戸東京博物館で、『主婦の生活の変化』のパネルが展示されていました。そこには、家庭家電製品の普及により、主婦の労働時間がどう変わったか、ということがまとめられていました。それによると、1915年(大正4年)家事労働時間は16時間6分、1961年(昭和36年)は10時間2分もかかっていたそうです。結構長い時間ですよね。
この家事に含まれるのは、大正の頃は
- 炊事・掃除
- 洗濯
- 洗張
- 裁縫
- 育児
- 買い物です。
昭和の頃になると、
- 炊事
- 掃除
- 洗濯
- 裁縫
- 買い物
*データは、「時間からみた一家5人の生活」(「婦人之友」第10巻第1号付録1950年)、稲葉ミナ・三東純子「共稼ぎ家庭と一般家庭の夫婦の生活時間的構造について」(「家政学雑誌」第14巻第3号1963年)より
育児を除く家事労働時は、1915年(大正4年)で12時間1分、1961年(昭和36年)7時間53分でした。
今のような家電が無いころは、家事は本当に大変な仕事だったんですね。
そして生まれた時間は、何に使われているのか?振り返る
現代の私の家事については、家電に助けてもらうことが増えてきました。炊事はヘルシオや、家電調理器具を使い作業時間減ってきました。掃除は、普段はおそうじロボットにお任せしています。ときどき気になるところは、別の掃除機を手動でかけています。
洗濯は、もちろん洗濯機ですが、最近は外に干す回数を減らし、乾燥までお願いしています。干す時間を短縮できるのと、タオルなどはそのまま横の収納に片づけてしまえるので、片付けまでの行動も早くできます。(2018年)2025年になると、子どもの服がかさばるため、乾燥機で一度に乾燥させるのは難しいため、外に干すことが増えています。子どもの成長に合わせて家事の仕方もかわりますね。
裁縫については、私自身はほとんどすることがありません。こどもの学校の事は、以前2018年の私はしていましたが、2025年になるとこどもが自分でできるものは本人にしてもらっています。ズボンの裾上げ、ボタンが外れたときは、自分でするよりきれいな仕上がりなのでお直しができるお店に持ち込んでお願いすることが多いです。
「買い物も宅配を使いお店に行く回数も減りました。買い物は、レジに並んだり、買い物かごをもって歩いたりと時間をとってしまうのと、ついつい余計なものを買ってしまうので、これからも宅配の利用が増えると思います。」と2018年は書いていましたが、2025年になると、これも子どもが大きくなったため、食べる量がかなり増えました。宅配は週に1度利用しつつ、残りは外出ついでに買い物をしています。
振り返って考えると、昔と比べるて家事の時間は家電やその他サービスを利用することでかなり短くなったのだと実感します。しかしその分生まれた時間は、「私は何に使っている?」のでしょうか。専業主婦もへってきていますし、仕事をしている人は、仕事の時間と往復の移動時間となていそうです。お仕事をしている人の場合は、お休みの日を振り返ってみて、家事以外の時間は何に時間を使っているか確認してみると発見がありそうです。
私はフリーランスで家で仕事をしているときもあれば、そうでないときもあります。たとえば1日を振り返ると
- 寝る時間7時間〜8時間
- 家事もろもろ2時間
- 食事・コミュニケーション2時間
- リラックス、お風呂他 1時間
のような感じで時間を使っています。そうすると、残り11~12時間あることになります。
12時間あれば色々できるはずなのですが、でも1日あっという間に過ぎて、思っている作業が終わらないこともあります。平日は、仕事とそれに伴う移動で大半の時間を取られる方もいると思います。私の場合は、自宅で仕事をしているので、その分自宅のときは使える時間が多いです。せっかく家電などに助けてもらって生まれた時間、家族とのコミュニケーションもとりつつ、自分の楽しむ時間ももちつつ、大事に使っていきたいなと思います。
私の時間をつくるためのスケジュールの工夫
このブログを最初に書いた2018年よりは、今の方が時間の使い方が上手になったように思います。こどもが大きくなったことも自由になる時間が増えた理由ですが、その増えた時間を自分が大事に思っていることに使いたいと考えています。私がスケジュールを考えるときに工夫していることを最後にご紹介します。
1.移動時間を減らす
今仕事以外にも、インテリアコーディネーターの協会の活動、PTAの委員などなどしています。
時間を有効に使いたい!といろいろ今試しています。一番効果があるのが、移動時間を少なくすることです。電車で移動することが多いのですが、電車は混んでいることが多いです。混んでないとある程度の事務連絡など出来ますが、ほぼ混んでいるので、人混みに疲れる、ネット環境が良くない、本も読みにくいので、最近は、選べるのであればなるべく移動時間が少なくなるようにしています。(2018年)
2025年になった今も、なるべく移動時間を少なくなるように心がけています。
2.朝の時間を有効に使う
朝は頭の働きがいい、といろいろなところで見かけます。以前からも知っていましたが、今試しているのは、朝の時間にメールを見ない、SNSを見ない、今日朝すると決めていたことをするという時間をもてるようスケジュールを立てています。もちろんお客様のところに行くなどの予定を入れることもありますが、なるべく朝の時間に集中できるようなスケジュールを心掛けています。(2018年)
これはやり方をかえつつ2025年今も続けています。なるべく朝に自分が大変と思うことや、難しいこと、考えないといけないことを取り組むようにしています。そして、出かけることや人と会うことは、午後の時間で予定を組むようにしています。朝は、頭の回転や働きが良い時間帯なので、それを活かすことで時間を有効に使いたいという思いからです。
3.TODOリストは永遠に消えないから、ライフビジョンを描いて大事なことに取り組む
TODOリストをつけていましたが、これが消えない。全部消えることがないのです。なんだか嫌になってきました。「1440分の使い方」ケビン・クルーズ著の本をよんで、「・・・やるべきこと、やれることは山のようにある・・・」と書かれていて、これでは時間を有効に使うのは難しいと理解しました。今していることは、TODOリストに上がっていた項目は、スケジュール帳の時間を割り当てて記入することにしました。あまり多くは詰め込まないように少しずつ書くようにしています。少しずつですが、時間の使い方がうまくなってきている実感はあります。(2018年)
2025年、TODOリストはgoogleカレンダーに書き込んで、取り組む時間を決めるようにしています。できないときは、別の日をまた設定して予定を移動させています。ただしその前に自分のライフビジョンを考えて、そこから逆算して今の自分に大事なことは何かを考えるようにしています。そうすることで、大事なことにも時間をつくり、行動に移せます。TODOリストは永遠に消えないのであれば、優先順位を考えることが大事だと気づきました。2024年には、書き込みできるライフビジョンノートをつくってみました。ライフビジョンってそんなに簡単に書けないので、いくつか質問に答えながら考えられるノートです。これを取り組んで、自分が考えていなかったことが見えた、これからの人生をどう取り組むか考えるきっかけになったと言っていただきました。私自身も、これを毎月と毎年見返してスケジュールを組んでいます。
4.自分プロジェクトをつくる
自分プロジェクトをつくるというのは、いろいろやりたいことがあってもなかなか進まないこと、時間がかかることについて、自分プロジェクトを立ち上げて管理することです。その時に役立つのがガントチャートです。リフォームの工事監理のときにも使いますが、長期にわたって計画をたてる必要があるものを管理するのに向いています。
みなさんは、どのようなことに時間を使っていますか?なかなか思い通りにいかないこともありますが、以前よりも家事の時間が減って時間が生まれているのであれば、その時間を使って自分の人生にとって有意義に過ごせる時間にしたいなと思います。